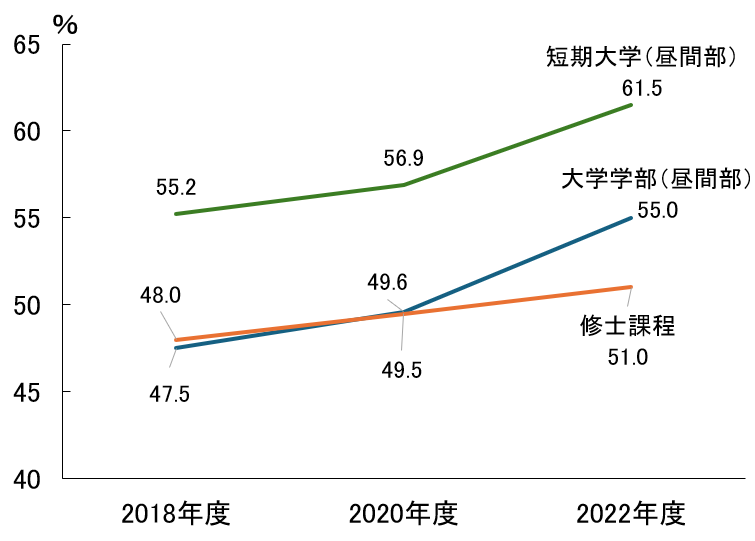「夢」を追い続けるハードロックの殿堂
潜望鏡 第10回
中学時代、ハードロックが大好きだった。だけど16歳までに、音楽の才能が全く無いという残酷な現実に気づく。凡人は大体、そんなものだろう。だが、世の中には幾つになっても粘り強く、「夢」を追い続ける人もいる。東京・六本木の路地裏にあるライブハウス「BAUHAUS」は、そんな夢が詰まった"タイムカプセル"である。毎晩、永遠のハードロック少年たちが集まり、名曲の数々を細部まで忠実に再現してくれる。一方、客は少年時代の自分に彼らを重ね合わせ、大音響とともに夢の空間へ引き込まれていく...
1971年、デイブ・ルイス(44)はフィリピン・ルソン島の田舎町で生まれた。9人きょうだいの8番目。両親は子どものために必死に働き続け、デイブはラジオから流れるビートルズやロッド・スチュアートを聴きながら大きくなった。学校を卒業すると首都マニラに向かい、レストランでウェイターとして働き始める。

ある日、デイブがキッチンで鼻歌に興じていると、客の一人が「歌手をやらないか」と誘ってきた。不安で一杯だったが、いつの間にか神様がデイブの背中を押していた。豊かな声量と幅広い声域を持つデイブにとって、ハードロックバンドのボーカルが天職となる。2000人収容のライブハウスで、デイブはエアロスミスやボン・ジョヴィを完璧にコピーしてみせ、客を熱狂させていた。
1997年、デイブに新たな転機が訪れた。「イメージを全く持っていなかった」という日本で仕事をするチャンスを得て、東京・錦糸町のフィリピン風の店で歌い始める。「日本食がダメだったから、もっぱら醤油ラーメンやマクドナルドのハンバーガーで空腹を満たしていた」―。店2階の1つの部屋で6人が寝泊りしたが、「とっても幸せだったよ、両親に仕送りもできたから...」―
デイブはフィリピン人の妻との間に3人の子宝に恵まれ、日本語で育てている。「日本食も好きになったし、東京は非常に安全な街。日本人は外国人に親切だし、学校で『おはようございます』といった挨拶を子どもに教えてくれることが素晴らしい」―。聞いていると恥ずかしくなるぐらい、デイブは大の日本びいきである。月曜から土曜まで、デイブはBAUHAUSのステージに立つ。「最も得意」というレッド・ツェッペリンの「移民の歌」は、全盛期のロバート・プラントに匹敵する切れと艶を感じる。だが、100キロを超える巨漢の何より凄い才能は、登場するだけで店内の空気を自分の味方にしてしまうことだ。
BAUHAUSの店長、各務亨(かがみ・とおる=40)は「デイブは他人との間に"壁"がないんです。初めてのお客さんとも親友みたいに接するのは性格なのか、それともエンターテインメントなのかよく分かりませんが...」と異能のボーカリストを評する。ドラム担当のダイスケ(32)も「デイブは人を幸せにする塊(かたまり)なんです。お客さんとつながらない調子の悪い時でも、魔法みたいに空気を変えちゃうんですよ。とても真似できない...」―

1981年の創業以来、BAUHAUSは幾多の困難を乗り越え、35年間にわたり六本木でハードロック文化を守ってきた。バンドのメンバーは礼儀正しいナイスガイばかり。一回30分のステージを5回こなし、その合間はウェイターやバーテンダーとして店を支えている。各務は「不景気になると人間は発散したくなるでしょ?だからリーマン・ショックも乗り切れたんです。もはやニューヨークにもこうした店はないらしいから、世界で唯一のハードロックの殿堂ですかね」と笑う。
今秋、バンドは10年ぶり2回目のロンドン公演に臨む。懐中電灯でメンバーの顔を照射しながら、クイーンの名曲「ボヘミアン・ラプソディ」を披露すれば、ロンドン子も間違いなく熱狂するだろう。店の経営は決して楽ではないと思うが、各務は若い頃から常に前向きな姿勢しか見せない。「毎日が楽しくて嬉しいんです。自分がやりたいことで稼げて生きているわけですから...」―。BAUHAUSはいつも「元気」をお土産にくれるから、翌朝二日酔いでも後悔したことがない。(敬称略)

(写真) 小笹 泰 PENTAX K-50等使用
タグから似た記事を探す
記事タイトルとURLをコピーしました!